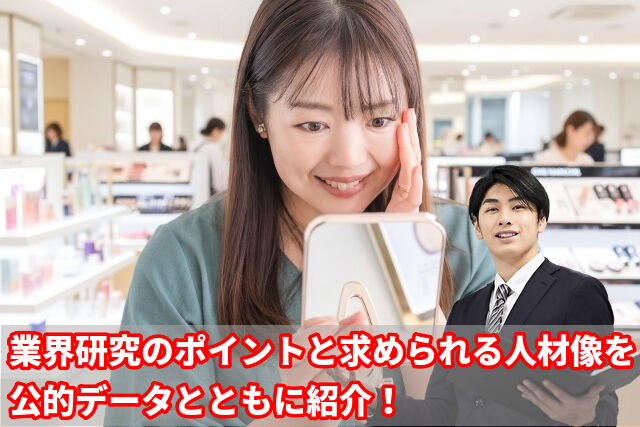化粧品業界の市場規模と成長トレンド
回復基調にある国内化粧品市場
化粧品業界は、コロナ禍による大きな打撃を受けた後、着実な回復を見せています。矢野経済研究所の調査によると、2023年度の国内化粧品市場規模はメーカー出荷金額ベースで前年度比104.6%の2兆4,780億円となりました。また、TPCマーケティングリサーチは2024年の市場規模を前年比2.6%増の2兆7,040億円と推計しており、市場の拡大傾向が鮮明になっています。
この回復を支える要因は複数あります。まず、2023年5月の新型コロナウイルス感染症の5類移行により、脱マスク化が進み、顔全体を見せる機会が増加したことでメイクアップ需要が回復しました。さらに、歴史的な円安を背景としたインバウンド需要の急増も市場拡大に大きく貢献しています。訪日観光客による化粧品購入は、百貨店やドラッグストアの売上を大きく押し上げる要素となっています。
将来予測も明るい兆しを見せています。矢野経済研究所は、2028年度の化粧品市場規模を2023年度比110.6%の2兆7,400億円まで成長すると予測しており、業界全体として持続的な成長が見込まれています。原材料コストの高騰による製品単価の上昇や高付加価値製品へのシフトも、市場規模拡大の一因となっています。
カテゴリー別の市場動向と注目領域
製品カテゴリー別に見ると、それぞれ異なる特徴が見られます。化粧品市場の約4割を占めるスキンケア分野は、市場の中核として安定した需要を維持しています。特に、しわ改善効果のある薬用化粧品の売れ行きが好調で、消費者の美容意識の高まりを反映しています。
メイクアップ分野では、コロナ禍で大きく落ち込んだ需要が回復傾向にあります。化粧水、美容液、日焼け止めなどの基礎化粧品が比較的順調な一方、つめ化粧品や香水・オーデコロンなどは低迷が続いており、明暗が分かれています。ヘアケア分野も総じて前年を上回る成長を見せており、トータルビューティーへの関心の高まりが窺えます。
特筆すべきは男性用化粧品市場の急成長です。富士経済の調査によると、メンズコスメ市場の規模は2024年には1,655億円まで拡大する見通しで、特に中高年層のスキンケア需要が伸びています。インテージの調査では、40代男性の基礎化粧品購入額が過去5年間で1.7倍に増加しており、ジェンダーレスな美容意識の浸透を示しています。
デジタルトランスフォーメーション(DX)が変革する販売チャネル
対面販売からオムニチャネル戦略へ
化粧品業界は従来、対面販売を強みとしてきましたが、コロナ禍を契機にデジタル化が急速に進展しています。業界の慣習として、顧客データは販売店が管理する仕組みとなっており、メーカーに共有されないという課題がありましたが、この壁を越えるべく各社が新たな取り組みを展開しています。
資生堂は2025年までにECの売上比率を40%に拡大する目標を掲げ、デジタルマーケティングに注力しています。同社は三越伊勢丹HDのECサイト「meeco」で初の国内ライブコマースをスタートさせたほか、オンラインwebカウンセリングやECプラットフォーム「omise+」を立ち上げました。さらに2022年9月には、複数の会員サービスを集約したアプリ「Beauty Key」をリリースし、店舗やECなどの販売チャネルを統合して顧客体験の向上を図っています。
花王もDX戦略を強化しており、2021年には新たにDX戦略推進センターとデジタル事業創造部を設置しました。これまでにないイノベーションを生み出すために、組織体制から見直しを図っています。マンダムも2021年5月にDX推進委員会を立ち上げ、業界全体でデジタル化への取り組みが加速している状況です。
AIとバーチャル技術の活用
デジタル化の進展において、AI技術とバーチャルメイク技術の活用が重要な役割を果たしています。これらの技術により、オンラインでありながら店頭と同等以上の顧客体験を提供することが可能になりました。
バーチャルメイクソリューションは、消費者が自宅にいながら様々な化粧品を試すことができる革新的なサービスです。特にコロナ禍において、「安心・安全」のために非接触型のサービスを求める消費者ニーズに応える形で急速に普及しました。花王のKATEブランドなどでは、バーチャルでメイクを試せるサービスを提供し、オンラインでのユーザー体験価値を高めています。
AI技術は、パーソナライズされた美容ソリューションの提供にも活用されています。ユーザーの肌の状態や悩みを分析し、最適な製品や使用方法を提案するAIカウンセリングサービスが登場しています。資生堂などの大手企業は、AI主導のデジタルソリューションを通じて、製品販売、プレミアムポジショニング、市場成長を促進しています。英国ユニリーバも2024年にAIを採用してカスタマイズされたユーザーエクスペリエンスを作成し、企業成長を推進する方針を示しています。
こうしたDXの取り組みは、単なるEC強化にとどまらず、実店舗とオンラインの良さを融合させたオムニチャネル戦略として展開されています。顧客データの一元管理により、チャネルを横断した一貫した顧客体験の提供が可能となり、顧客満足度の向上とブランドロイヤルティの強化につながっています。
サステナビリティと環境配慮型ビューティーの台頭
化粧品産業ビジョンに見る業界の方向性
2021年4月、経済産業省と日本化粧品工業連合会は、日本の化粧品産業の競争力強化と継続的な発展を目指し、産学官による初の「化粧品産業ビジョン」を策定しました。このビジョンでは、化粧品業界として「持続可能な社会の実現をリードする産業となる」という方向性が明確に示されており、環境問題や人権問題への積極的な取り組みが業界全体の重要課題として位置づけられています。
具体的には、多様な人材の活用、ジェンダー平等の実現、SDGsへの積極的な貢献などが掲げられています。世界的なサステナビリティ意識の高まりを受け、化粧品業界においても環境配慮と社会的責任が競争力の源泉となりつつあります。特に欧米市場では、サステナブルな製品開発や企業姿勢が購買決定に大きく影響するようになっており、グローバル展開を目指す企業にとって避けては通れないテーマとなっています。
容器包装とプラスチック削減への取り組み

化粧品業界における環境配慮の取り組みで、最も注目されているのが容器包装のサステナビリティです。日本化粧品工業会は「化粧品の容器包装に関する環境配慮設計指針」を策定し、業界全体で容器包装プラスチック使用量の削減に取り組んでいます。
資生堂は、2020年に資源効率性の向上とサーキュラーエコノミーの実現を目指して独自の容器包装開発ポリシー「資生堂5Rs」を定め、2025年までに100%サステナブルな容器を実現するという目標を掲げています。2024年末時点で76%をサステナブルな容器へ切り替えており、さらに2030年までに製品あたりのプラスチック製容器の30%をリサイクルプラスチック(PCR)またはバイオマス由来プラスチックから製造することを目標としています。
つめかえ・つけかえ容器によるリユースの促進、モノマテリアル化によるリサイクル可能な設計、容器の軽量化など、具体的な施策が進められています。世界的には、ロレアルと先進的なサステナビリティ・コンサルティング「クアンティス」が化粧品業界の新たなイニシアティブ「SPICE(Sustainable Packaging Initiative for Cosmetics)」を立ち上げ、業界横断的な取り組みも始まっています。
原料調達と製品開発における環境配慮
容器包装だけでなく、原料調達や製品開発のプロセス全体においても環境配慮が進んでいます。日本化粧品工業会のサステナビリティ推進委員会では、持続可能な調達をテーマとした参加型プログラムを開催し、会員企業間で知見を共有しています。
アルビオンは白神山地の麓に畑を有し、無農薬自社栽培を実施するなど、原料植物の持続可能な確保に力を入れています。また、動物実験の代替手法の開発や、生産工場における第三者機関による品質・安全性チェックの実施など、製造工程全体での環境負荷軽減と安全性確保が進められています。
日本ロレアルは、2013年に「SHARING BEAUTY WITH ALL」というコミットメントを発表し、世界中の200以上のNPO組織と社会的課題について議論を行いながら、環境・社会への取り組みを進めています。継続的に150以上の組織と意見交換を実施し、ステークホルダーとの対話を重視した活動を展開しています。
就職市場と採用動向

売り手市場が続く化粧品業界の就職状況
化粧品業界への就職は、依然として高い人気を誇る一方で、業界全体として人材確保が課題となっています。2024年度の美容業界の新卒採用は、学生が企業を選べる「売り手市場」の傾向が続いています。化粧品業界は女性を中心に高い人気があり、就活で志望者が集中しやすい業界として知られていますが、企業側も優秀な人材の獲得に向けて積極的な採用活動を展開しています。
美容部員の新卒採用においては、例年3月にエントリーが開始され、エントリーシートの提出、Webテストの受験、グループワーク、面接を経て内定に至る流れが主流です。政府も「会社説明会受付などは3月1日以降、面接などの採用選考は6月1日以降」と定めており、早い企業では6月上旬には採用予定通知が出されています。
資生堂ジャパン、コーセー、日本ロレアル、P&Gプレステージなど大手企業では、ブランド別の採用を実施しているケースも多く、配属や働き方がブランドごとに異なる点が特徴です。これにより、学生は自分の志向に合ったブランドを選択できる一方、各ブランドの特性や企業文化を深く理解することが求められます。
業界が求める人材像とスキル
化粧品業界が求める人材像は多様化しています。美容や化粧品への深い興味と愛は基本的な要素ですが、それに加えて以下のようなスキルや資質が重視されています。
第一に、デジタルリテラシーとDX推進力です。業界全体がデジタル化を進める中、ECサイトの運営、SNSマーケティング、データ分析、AI技術の活用などに関する知識やスキルが求められています。特に若い世代は、InstagramやTikTokなどのSNSに精通しており、デジタルネイティブとしての感覚が強みとなります。
第二に、サステナビリティへの理解と実践力です。環境問題や社会課題に対する意識の高さ、SDGsへの関心、エシカル消費への理解などが評価されます。企業の環境配慮型製品開発や社会貢献活動に共感し、自ら考えて行動できる人材が求められています。
第三に、グローバル視点とコミュニケーション能力です。化粧品業界は国際的な広がりを持つ産業であり、多様な文化や価値観を理解し、異なるバックグラウンドを持つ人々と協働できる能力が重要です。語学力はもちろん、異文化理解力や柔軟な思考力が求められます。
第四に、顧客志向とホスピタリティです。美容部員として働く場合、お客様一人ひとりの肌悩みに寄り添い、最適な商品やアドバイスを提供する力が必要です。傾聴力、提案力、共感力などのコミュニケーションスキルが重要視されます。
キャリアパスと働き方の多様化
化粧品業界のキャリアパスは、従来の販売職から管理職へという単線的なものから、多様なキャリア選択が可能な環境へと変化しています。美容部員からスタートし、店長、エリアマネージャーへとステップアップする道に加えて、商品企画、マーケティング、デジタル戦略、サステナビリティ推進など、様々な専門職へのキャリアチェンジの機会が広がっています。
働き方の面でも改革が進んでいます。大手企業を中心に、ライフステージに応じた柔軟な働き方が選択できる仕組みが整備されつつあります。P&Gなどは福利厚生が充実しており、社員のワークライフバランスを重視した制度を導入しています。女性管理職の積極登用や「子育てサポート企業」の認定取得など、ジェンダー平等の実現に向けた取り組みも進んでいます。
ただし、美容業界には離職率の高さという課題も存在します。リクルートの「美容サロン就業実態調査(2024年)」によると、美容師の初職就業期間は3年未満が36.7%に上り、給与に関する不満、職場環境や人間関係への不満などが離職理由として挙げられています。そのため、新卒採用時のミスマッチを解消することや、入社後の待遇改善が業界全体の重要課題となっています。
グローバル市場と国際競争
世界市場における日本の化粧品の立ち位置
世界の化粧品市場規模は、2024年に335.95億ドルと評価され、2025年の354.68億ドルから2032年までに556.21億ドルに成長すると予測されています。年平均成長率(CAGR)6.64%で着実に成長する見込みで、特にアジア太平洋地域が2024年に市場シェアの39.57%を占め、グローバル市場を牽引しています。
日本の化粧品は高品質で知られ、国際的な評価も高く、特にスキンケア製品は世界中で人気を博しています。財務省貿易統計によると、化粧品の輸出入金額については、長期にわたり輸入金額が輸出金額を上回る状態が続いていましたが、2015年から輸出金額が急増し、2016年に初めて輸出金額が輸入金額を超えました。さらに2018年からは輸出金額が輸入金額の2倍強となっており、日本製化粧品の国際競争力の高さを示しています。
しかし、アジア圏では韓国や中国などのブランドの成長が著しく、今後は競合が激化すると予測されています。韓国コスメ(K-Beauty)は、革新的な製品開発とSNSマーケティングの巧みさで世界的な人気を獲得しており、中国コスメも急速に品質を向上させています。日本企業が国際競争で優位性を維持するためには、技術力の高さに加えて、ブランディング戦略やデジタルマーケティングの強化が不可欠です。
インバウンド需要の影響と今後の展望
インバウンド需要は日本の化粧品市場に大きな影響を与えています。2024年の市場拡大には、歴史的な円安の影響を追い風としたインバウンド需要の回復が大きく寄与しました。訪日観光客は徐々に増加しており、特に百貨店やドラッグストアでの化粧品購入が売上を押し上げる重要な要素となっています。
2023年以降、新型コロナウイルスによる行動面の制限や消費者の買い控えなどの経済面への影響も落ち着きを見せ、インバウンド需要も順調に回復しています。百貨店チャネルでは、インバウンド好調により2ケタ伸長を記録するなど、外国人観光客の購買力が市場に与える影響は極めて大きくなっています。
ただし、インバウンド需要に過度に依存することはリスクも伴います。為替変動や国際情勢の変化により、需要が急激に変動する可能性があるためです。そのため、国内需要の安定的な確保と海外展開の強化を両立させる戦略が重要となっています。日本企業は、国内市場での強みを活かしながら、アジアをはじめとする海外市場での存在感を高めていく必要があります。
業界研究で押さえるべきポイント
企業選びの基準と比較検討のポイント
化粧品業界への就職を目指す学生にとって、自分に合った企業を選ぶための明確な基準を持つことが重要です。以下のポイントを考慮して企業を比較検討しましょう。
1. 企業のビジョンと価値観
各企業が掲げるビジョンやミッション、企業文化が自分の価値観と合致しているかを確認します。サステナビリティへの取り組み、ダイバーシティ推進、社会貢献活動などの姿勢も重要な判断材料です。
2. 製品ラインナップとブランド戦略
取り扱う製品カテゴリー(スキンケア、メイクアップ、ヘアケアなど)やターゲット顧客層、価格帯などを理解します。
さらに商品に対する評価も認識しておきましょう。
例えばディー・アップ製品の口コミは『Loft』やAmazon等のショッピングサイトで知ることができます。自分が関心を持つブランドや製品領域があるかを確認しましょう。
3. キャリアパスと成長機会
入社後のキャリアパスが明確か、教育研修制度が充実しているか、専門性を高める機会があるかなどを調べます。国内外への異動や職種転換の可能性についても確認しておくと良いでしょう。
4. 働き方と福利厚生
勤務時間、休日日数、育児・介護支援制度、在宅勤務の可否など、ワークライフバランスを保てる環境が整っているかを確認します。女性管理職比率や育休取得率なども重要な指標です。
5. デジタル化への取り組み
EC展開、DX推進、AI活用などの先進的な取り組みを行っているかも、将来性を見極める上で重要です。デジタル人材の育成に力を入れている企業は、成長機会も豊富です。
業界研究の実践的アプローチ
効果的な業界研究を行うためには、多角的な情報収集と分析が必要です。以下の方法を組み合わせて、業界への理解を深めましょう。
まず、公式情報の収集から始めます。企業の公式ウェブサイト、統合報告書、サステナビリティレポート、採用ページなどは最も信頼性の高い情報源です。
またディー・アップの様に公式XやInstagramなどのSNSも重要な収集減です。
さらに経済産業省や日本化粧品工業連合会などの公的機関が発表する業界レポートや統計データも必ず確認しましょう。矢野経済研究所や富士経済などの調査会社のレポートも、市場動向を把握する上で有用です。
次に、業界専門メディアのフォローが効果的です。週刊粧業オンライン、ビューティー業界ニュースサイト、日経クロストレンドなどを定期的にチェックすることで、最新のトレンドや企業動向を把握できます。業界の変化は速いため、リアルタイムの情報収集が重要です。
企業説明会やインターンシップへの参加も貴重な機会です。実際に企業の雰囲気を感じ、社員と直接対話することで、ウェブサイトからは得られない生の情報を得られます。可能であれば複数の企業のイベントに参加し、比較することで自分に合った企業を見極めやすくなります。
さらに、店舗訪問による実地調査も推奨されます。百貨店、ドラッグストア、専門店などで実際に製品を見て、販売員の接客を体験することで、各ブランドの特徴や顧客対応の違いを肌で感じることができます。競合他社の製品も含めて幅広く観察することで、業界全体の理解が深まります。
まとめ:変革期の化粧品業界で求められる姿勢
化粧品業界は現在、デジタル化とサステナビリティという二つの大きな変革の波の中にあります。市場規模は着実に成長し、2028年度には2兆7,400億円に達すると予測される一方で、業界の構造や競争環境は大きく変化しています。
就職を目指す学生にとって、この変革期はチャンスでもあります。DXの推進により新しい職種が生まれ、サステナビリティへの取り組みが新たな価値創造の源泉となっています。従来の販売職だけでなく、デジタルマーケティング、データ分析、サステナビリティ推進など、多様なキャリアパスが開かれています。
重要なのは、業界の変化に柔軟に対応できる力を身につけることです。デジタルリテラシー、グローバル視点、サステナビリティへの理解、そして何より美容への情熱と顧客志向の姿勢が求められます。変化を恐れず、むしろ変化を楽しみながら成長していける人材が、これからの化粧品業界では活躍できるでしょう。
株式会社ディー・アップをはじめとする化粧品企業は、それぞれ独自の強みと戦略を持って市場に挑んでいます。業界研究を通じて各社の特徴を理解し、自分の価値観やキャリアビジョンに合った企業を見つけることが、充実した就職活動の第一歩となります。
本記事で紹介した市場動向、デジタル化の進展、サステナビリティへの取り組み、採用動向などの情報を参考に、ぜひ深い業界理解を構築してください。そして、変革期だからこそ生まれる新しい可能性に目を向け、自分らしいキャリアを化粧品業界で築いていただければと思います。